近年、日本の中小企業や農業・介護・建設など様々な業種で「外国人技能実習生」という言葉を耳にする機会が増えています。人手不足の解消手段として注目される一方で、「実習って何をするの?」「労働力確保が目的なのでは?」といった疑問や誤解もあるようです。
この記事では、「外国人技能実習」とは何か、どんな目的で行われているのか、実習生の受け入れ方法や注意点まで、わかりやすく解説します。
外国人技能実習制度とは?
技能実習制度の概要
外国人技能実習制度とは、発展途上国の若者が日本で一定期間、実際の業務を通じて技能・技術・知識を習得する制度です。日本の先進的な技能を実地で学び、それを母国の発展に活かしてもらうことを目的としています。
制度の位置づけ
この制度は、単なる労働力確保ではなく「国際貢献」の一環とされています。日本の企業が持つ高度な技能を外国人に伝えることで、彼らの母国の経済発展や産業育成に寄与することが期待されています。
技能実習制度の目的
人材育成による国際貢献
技能実習制度は、1993年に創設されました。当初から制度の根幹にあるのは「国際協力」「人材育成による国際貢献」という理念です。技能を学んだ実習生が母国に戻り、それぞれの地域の発展に貢献することを目指しています。
人手不足対策という現実的側面
理念としては国際貢献が前提ですが、実際には日本国内の人手不足を補う役割も担っています。特に地方や中小企業、3K(きつい・汚い・危険)と呼ばれる業種でのニーズが高く、農業・建設・製造・介護などが代表的な受け入れ業種です。
技能実習制度の仕組みと流れ
実習期間
外国人技能実習は最大で5年間滞在可能です。段階的に区分されており、以下のように進行します。
- 技能実習1号(1年目):基礎的な技能の習得
- 技能実習2号(2~3年目):応用的な作業を学ぶ
- 技能実習3号(4~5年目):より高度な技能の習得(条件を満たす場合のみ)
受け入れ機関の形態
外国人技能実習生は、以下の2つの形態で受け入れられます。
① 団体監理型(大多数)
商工会や協同組合などの監理団体が実習生と企業の橋渡しを担います。中小企業や地方事業者ではこの方式が中心で、団体が定期的に巡回指導や報告を行います。
② 企業単独型
海外の取引先やグループ会社などから直接実習生を受け入れる方式です。大企業や国際展開している企業で多く見られます。
実習生の選考と入国までの流れ
- 海外の送出し機関で候補者を募集
- 書類選考・オンライン/現地面接で適性を見極める
- 日本語・生活習慣などの事前教育(数ヶ月間)
- 日本入国後の講習:約1か月(日本語・安全衛生・労働法など)
- 企業への配属後、OJTを通じた実践的な技能習得がスタート
実習可能な職種と業種
技能実習制度では、実習可能な職種が法律で定められています。2025年時点で、約80職種・150作業以上が対象となっています。
代表的な業種には以下のようなものがあります。
- 農業(畑作、施設園芸、養豚など)
- 建設業(鉄筋施工、型枠施工、とび作業など)
- 製造業(鋳造、機械加工、プラスチック成形など)
- 食品製造業(パン製造、惣菜加工、水産加工など)
- 介護(施設介護、訪問介護など)
技能実習制度のメリットと課題
受け入れ企業にとってのメリット
- 人手不足の解消:
地方や3K職場では人材確保が困難です。実習生の受け入れにより、現場の稼働率が向上し、急な欠員にも迅速に対応できます。 - 職場の国際化・活性化:
実習生を通じて新たな視点が入り、社内コミュニケーションが活発化。異文化理解が深まり、多様性を尊重する職場文化が育ちます。 - 社員の教育意識の向上:
教える立場になることで、社員自身の業務理解が深まり、マニュアル整備や伝達力向上にもつながります。
実習生にとってのメリット
- 高水準な技能を習得できる:
日本の高度な現場での経験は、帰国後の就職や起業活動に大きな武器となります。 - 安定した収入を得ながら働ける:
日本の収入水準は母国に比べて高く、貯金や仕送りによって家族の生活向上に貢献できます。 - 日本での生活・文化を体験できる:
日本語力や生活習慣、職場マナーを身につけ、国際感覚を養う貴重な機会になります。
制度上の課題と批判
- 賃金や労働環境の不備:
一部の事業所では最低賃金以下で働かせる事例や、残業代の未払いなどが報告されています。監査強化や罰則導入の必要性が叫ばれています。 - 長時間労働やパワハラの問題:
実習生が弱い立場に置かれるケースで、過重労働や不当な叱責なども報告されています。企業側の意識改革と団体・行政による支援強化が必要です。 - 実習という名目の労働搾取の懸念:
技能移転よりも労働力確保が優先される場面があり、「実習制度の趣旨逸脱」との批判があるため、制度見直しが進められています。
技能実習と「特定技能」との違い
| 比較項目 | 技能実習 | 特定技能 |
|---|---|---|
| 目的 | 技能の習得と母国への移転 | 即戦力の外国人労働者確保 |
| 滞在期間 | 最大5年(段階的に延長) | 最大5年(業種により永住も可能) |
| 職種制限 | 定められた職種のみ | より広い業種に対応 |
| 転職の可否 | 原則不可(実習先固定) | 一定条件で可能 |
実習生受け入れの流れと注意点
企業が実習生を受け入れる手順
- 監理団体の選定と契約:
監理団体は実習全般の管理・教育・行政対応を担います。信頼性・支援体制・実績を重視して選びましょう。 - 実習計画の策定と申請(外国人技能実習機構):
実習内容・期間・教育方法を明記した計画書を作成。外部の審査を通過しなければ実習は始まりません。 - 送出し機関と連携して人材募集・選考:
ベトナム・インドネシア・ミャンマーなどで政府認可の機関と連携し、日本語・技能・適性を基に選考します。 - 在留資格の取得と受け入れ準備:
入国管理局への申請と企業側の受け入れ準備(住居環境、講習施設など)を行い、安全かつ円滑な受け入れ態勢を整えます。 - 講習終了後に配属、実習スタート:
入国後の講習が終わると企業に配属され、本格的なOJTに入ります。現場環境への配慮と段階的な育成が鍵です。
注意すべきポイント
- 適正な労働環境・安全衛生の確保:
労働基準法や安全設備の基準を満たすことは必須。定期的な安全教育、保護具の支給、事故防止策は欠かせません。 - 実習計画通りに教育・指導を行う:
働かせるのではなく、学ばせることが法の趣旨です。段階的なOJT、定期的な評価やフォローアップで学びを可視化しましょう。 - 実習生とのコミュニケーションを大切に:
言語・文化の壁を乗り越えるために、通訳サポートや定期的な面談、相談窓口を設置し、心のケアも含めた支援が必要です。
今後の展望と制度改革の動き
政府は技能実習制度を見直し、「育成就労制度」へと刷新する方針を打ち出しています。新制度では、より実効性のある人材育成と労働力確保の両立が目指されており、転職の自由や処遇改善、キャリア形成支援がキーワードとなっています。
2025年以降、この分野の制度や受け入れ環境は大きく変わる可能性があるため、企業・監理団体ともに最新の情報収集と対応が求められます。
まとめ
外国人技能実習制度は、日本の技能を世界に伝える「国際貢献」の制度でありつつ、現実には労働力としての役割も担っています。実習生・企業双方にとってメリットのある制度ですが、適切な運用と人道的な配慮が不可欠です。
今後は新制度への移行も視野に入れ、より良い国際人材育成の在り方が問われる時代になっていくでしょう。制度の目的や仕組みを正しく理解し、健全な受け入れを目指すことが何より重要です。
おすすめの監理団体を紹介
団体監理型で技能実習生を受け入れるなら、信頼できる監理団体を利用したいですよね。今回は数ある監理団体の中から、「WorldLink技能交流事業協同組合」(以下、World Link)をご紹介します。
World Linkは優良一般監理団体・特定技能支援機関です。信頼できる送り出し機関との協定、実習生へのこまめなヒアリング、企業との密な連携とサポートなど、信頼関係を大切にした取り組みで、「途中帰国ゼロ、失踪ゼロ」を目指しています。
この取り組みが成果を上げていて、介護職以外の実習生のうち60%が建設、30%が工場(製造)、10%が農業で受け入れていますが、逃亡が多い建設、農業の実習生が多いにも関わらず失踪者を出していません。
実習生からも企業からも信頼と高い評価を受けているWorld Linkは、これから技能実習制度を利用する企業にとって心強いパートナーになってくれるでしょう。
Worlk Link 技能交流事業協同組合の基本情報
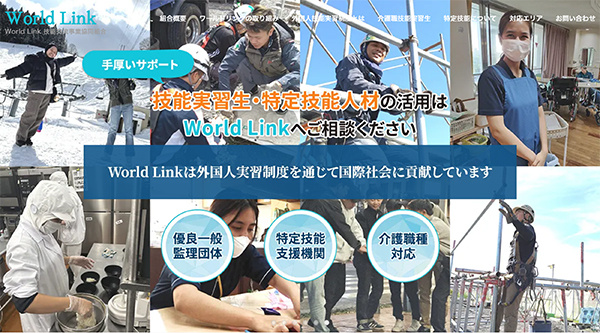
| サイト名 | World Link |
| 組合名 | World Link 技能交流事業協同組合 |
| 所在地 | 〒676-0824 兵庫県高砂市阿弥陀町南池452-2 |
| 問い合わせ先 | 電話:079-446-9000またはサイト内メールフォーム |
| 支援内容 | 外国人技能実習生・介護技能実習生・特定技能外国人の招致 現地日本語学校/送り出し機関へ学習費用・寮費・食費の全額支援 研修・継続的な見守り 機構・入国管理局への申請書類作成 企業の希望に沿った実習生のマッチング 無料実習生受け入れセミナーなど |
| 対象国 | ベトナム・ミャンマー・中国・インドネシア・カンボジア |
| 紹介先企業の地域 | 兵庫県内 |
| 一般監理団体許可番号 | 許1708001688 |
| 有料職業紹介許可番号 | 28-ユ-301059 |
| 無料職業紹介許可番号 | 許28-特000062 |
| URL | https://worldlink-union.jp/ |

コメントは受け付けていません。
トラックバックURL
https://www.4touristinfo.com/company/118/trackback/